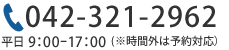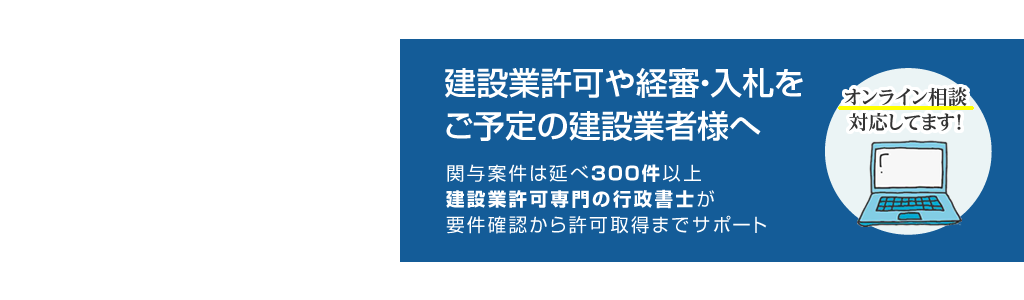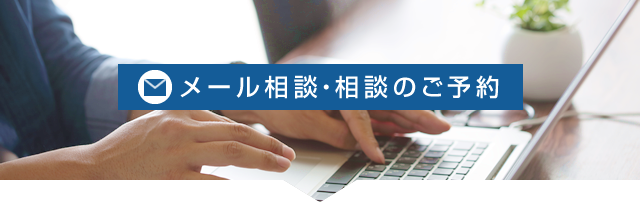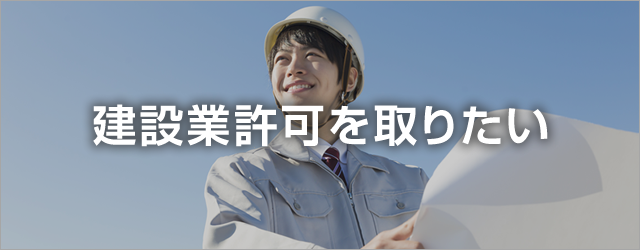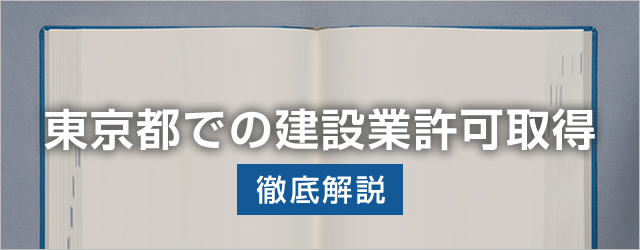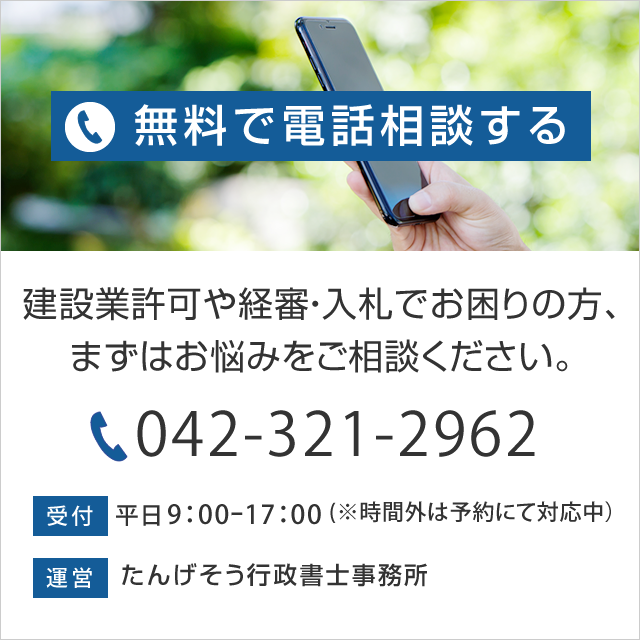~法改正の最新情報とその影響を徹底解説~
建設業を営む上で欠かせない建設業許可。その取得や維持をお考えの皆様に、2024年6月に施行された「第三次・担い手3法」を中心に、法改正の詳細や業界への影響を分かりやすくご案内します。法改正への対応は、企業の持続的な成長と信頼性の確保に直結します。この機会にぜひご確認ください。
以下の記事をお読みになって、今後の公共工事の受注や社内整備等をより一層なさっていきたい業者様は是非「たんげそう行政書士社会保険労務士事務所」にご相談いただければと思います。
まずそもそも「担い手3法」とは何か?を説明させて頂きます
「担い手3法」というのは、建設業に関わる3つの法律のことで、建設業界で働く人たち(=担い手)の働きやすい環境を整えたり、将来も建設業が続いていけるようにするための仕組みを作る法律です。2024年に改正されたものが「第三次・担い手3法」と呼ばれています。
具体的には次の3つの法律です:
1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)
- 何をする法律か?
公共工事(道路や橋など)の品質を良いものにしつつ、働く人たちの労働条件を良くする法律です。 - 具体的には?
安全で確実な工事を進めるために、無理なスケジュールや低い給料で仕事を押し付けないようにします。
2. 建設業法
- 何をする法律か?
建設業で働く人たちがスムーズに仕事をできるようにルールを作り、業界全体の健全な発展を目指す法律です。 - 具体的には?
例えば、技術者が必要以上に現場に縛られないようにするなど、柔軟な働き方ができるように改善されました。
3. 入札契約適正化法(入契法)
- 何をする法律か?
建設工事の契約を公平で適正なものにするための法律です。 - 具体的には?
発注者(工事を依頼する人)が適正な金額や条件で仕事を依頼するようにします。これにより、工事を請け負う業者が無理なく働けるようになります。
簡単に言うと…
「担い手3法」は、建設業で働く人たちが「ちゃんと休めて」「適正な給料がもらえて」「安全に仕事ができる」環境を作るための法律です。道路や建物などを作るのに大切な仕事だからこそ、働く人たちを大事にしよう、という考えに基づいています。
これらの法律が守られると、未来の建設業で働く人が安心して仕事を続けられるようになります!
1. なぜ法改正が行われたのか?
建設業界が直面する課題
建設業は、道路や建物、災害復旧など、私たちの生活を支える重要な役割を担っています。しかし、労働環境の厳しさや就業者の高齢化・減少が深刻化し、業界全体の持続可能性が危ぶまれています。これに対応するため、労働環境の改善、人材育成、生産性向上を目的とした改正が行われました。
2. 法改正の主なポイント
1. 担い手の確保
- 休日確保の推進
労働者の負担軽減を目指し、国が現場の実態を調査。必要な施策を講じることで、定期的な休日取得が推奨されます。 - 処遇改善の取り組み
労務費や賃金支払の実態調査を通じ、スキルや能力に応じた適切な給与の支給を目指します。 - 人材育成環境の強化
長期的な視点での技術者育成と、女性や若年層など多様な人材が活躍できる環境作りを進めます。
2. 生産性の向上
- 新技術の活用
ICT技術(例:ドローンや建設機械の自動化)の導入が奨励され、作業効率を大幅に向上させます。 - 脱炭素化の推進
環境負荷を軽減する技術の普及を支援。省エネ施工の普及を通じて、持続可能な建設業を目指します。
3. 地域建設業の対応力強化
- 災害対応力の向上
地域に密着した建設業者が効率よく災害復旧に対応できる体制を整備します。 - 入札・契約の適正化
発注者支援の充実により、地域の実情に応じた適切な発注が可能に。無理のない契約内容で作業が進められます。
3. 今後の施行スケジュール
- 2024年6月19日施行
品確法等の改正部分がスタート。測量法の一部改正は2025年4月1日に施行予定です。 - 2024年6月14日から段階施行
建設業法や入契法の改正内容が施行開始。施行完了は2025年12月までを予定しています。
4. 改正の影響と対応策
法改正に伴い、以下のような対応が求められます:
- 技術者配置の見直し
技術者の効率的な配置が可能となる一方、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が推奨されます。 - 契約条件や事務手続きの見直し
施工体制台帳提出の省略など、事務負担軽減の恩恵を受けるための準備が必要です。 - 労働環境改善への積極的な取り組み
法改正の趣旨を活かし、休日取得の管理や労働者の処遇改善に積極的に取り組みましょう。
5. 最新情報の確認方法
- 国土交通省公式サイト
最新の法改正情報やガイドライン、Q&Aが公開されています。
参考サイト
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000193.html
- 専門家への相談
行政書士などの専門家と連携することで、具体的な手続きや対応策をスムーズに進められます。
まとめ
建設業許可を取得・維持するためには、法改正の内容を正確に理解し、迅速に対応することが不可欠です。これにより、企業としての信頼性を高めるとともに、持続可能な成長が期待できます。ぜひ最新の情報を活用し、適切な準備を進めてください。
担い手育成≒貴社の今後の発展です。会社内の処遇の改善などは社労士でもある丹下も一緒に考えさせていただければと思っておりますので、是非ご相談いただければと思っております。